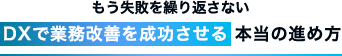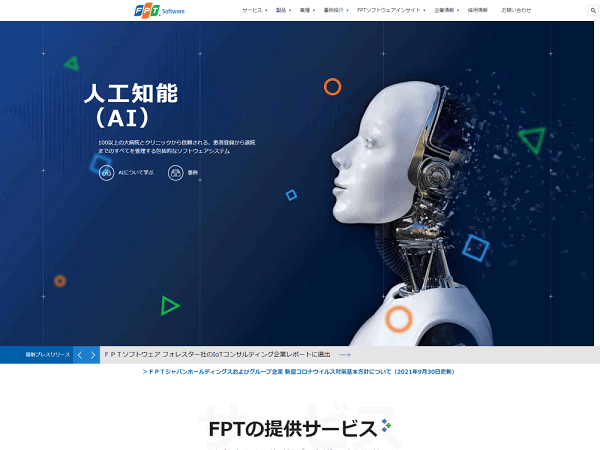NEC
日本の製造業において代表的な企業でもあるNECは、自社のノウハウを活用したコンサルティングも提供。大手が培ったノウハウや製作したシステムを利用できます。
NECが支援するDXとは?
製造業サイクルシステムを提供し、DXによる業務効率化をサポートしてくれるNEC。
製造業の重要スタッフを設計業務から解放し、新商品開発業務などに注力させた事例が多くあります。
製造工程プロセスをDXで改革したいと検討している企業におすすめです。
NECのDXの業務改善事例
独自のシステム導入で効率化し別業務へ注力できるように
自動車業界全体の流れに合わせてグローバル化を検討しているが、製造プロセスと品質を一貫されていない状況。
拠点によって異なる品質や単価の統一化とプロセスを効率化して新商品開発に力を入れたいという点が目標でした。
拠点ごとに管理していた部品表や他情報を統合し、NECの製造サイクルシステム「NEC PLM Obbligato」に集約。
デジタルを活用した業務効率化に成功し、技術開発に注力できるようになりました。
顧客入力による設計の自動化に成功し開発者が別業務に注力
豊富な種類の製品を受注設計で少量ずつ販売するビジネスモデルでしたが、利益的に厳しいと感じるようになっていました。
大量在庫となっている部品も流用すれば節約できそうな部分があり、組み合わせて設計するモジュラーデザインを検討するもうまくいかない状況でした。
顧客が希望の仕様を入力するコンフィグレータを導入し、NECの独自システムObbligatoに反映させて設計を自動化する仕組みづくりに成功。
設計者は戦略業務に力を入れ、他社との差別化に成功しています。
このサイトでは、NECの他にも、DXで業務改善を支援するコンサル会社、SIerを紹介しています。
TOPページでは「DXに取り組んでいるが現場に浸透しない」「成果の振り返りができておらずPDCAを回せていない」などの課題がある企業のDX推進部門の担当者向けに、DX で業務改善に至るまで伴走する中堅コンサル会社、SIerを紹介していますので、参考にしてください。
DXで業務改善に至るまで伴走する
中堅コンサル会社、SIer3選
NECの特徴
戦略に沿った自動化が可能なシステムを提供
NECのコンサルティングは製造業のDXを支える国産のシステム「NEC PLM Obbligato」の導入に力を入れています。
「NEC PLM Obbligato」は企画、設計、生産そして保守まで製造業において必要な工程を一貫して管理できるシステムです。
製品のパッケージ化から顧客要望を踏まえた個別開発まで幅広く対応できるため、少ない製品を多く販売する戦略や個別に受注対応する戦略など柔軟に対応できます。
日本を代表する企業からのサポートで戦略を強化できる
自社も大手メーカーとして20年以上に渡り日本を引っ張ってきたNECは、過去の実績で積み重ねてきたノウハウで製造業をサポート。
社内業務の改善だけでなく、社外向けアピールに有効なDX認定の取得を支援する体制も整っています。
NECのコンサルタント紹介
桃谷 英樹
NECにおけるリードコンサルタントとしての活躍に加えて、外資企業にて戦略コンサルティングのリーダーも務めています。
自身が責任者として経験したコンサルティングプロジェクトは450以上(2022年9月時点)にも及びます。
NECの基本情報
| 所在地 |
東京都港区芝5−7−1 |
| 電話番号 |
03-3454-1111 |
| 受付時間・定休日 |
土曜日、日曜日・祝日・他休業日 |
| 会社名 |
日本電気株式会社 |
| 公式HPのURL |
https://jpn.nec.com/ |
机上のアウトプットだけでは終わらない!
DXで業務改善に至るまで
伴走する中堅コンサル会社
DX企画や戦略立案を机上で示すだけでなく、プロジェクトの一員として機動的にサポートするのが中堅コンサル会社の特徴です。ここでは目的別に数多くの企業に実績があるDX中堅コンサル会社を厳選してご紹介します。
引用元:ベルテクス・パートナーズ
https://www.vertex-p.com/
こんな企業におすすめ
新規事業のアイデア創出、現場へのアプローチ、DXの自走化支援など、組織変革のきっかけを作りたい企業
DXの特徴
- 変革を阻む"組織の壁"に対し、企業の特性に応じてアプローチ
- 経営層と現場に成功体験を共有し、DXを継続的に取り組める組織へ変革
ベルテクス・パートナーズの公式HPでDXで業務改善した事例を見る
DXの特徴を詳しく見る
引用元:RIT
https://www.rit-inc.co.jp/
こんな企業におすすめ
アプリケーションや業務管理ツールなど業務のデジタル化を起点とするDXを推進したい企業
DXの特徴
- 独自のDX診断サービスを実施し、費用対効果の高いツールを提案
- "バーチャルDX推進室"にて、企業のデジタル化をバックアップ
RITの公式HPでDXで業務改善した事例を見る
DXの特徴を詳しく見る
引用元:FPTソフトウェアジャパン
https://www.fpt-software.jp/
こんな企業におすすめ
勘定系システム、クラウドサービスなど業務の根幹となるシステム開発・更改を起点とするDXをしたい企業
DXの特徴
- 多業種のシステム開発の実績が豊富、フルスクラッチ開発からリプレイスまで対応可能
- ビジネスコンサル会社と協業し、システムと経営の両面からDXをサポート
FPTソフトウェアジャパンの公式HPでDXで業務改善した事例を見る
DXの特徴を詳しく見る
【このサイトに掲載する企業の選出基準】
2022年7月12日時点、「DX 業務改善」とGoogle検索して表示されたコンサルティングファーム、SIer(システムインテグレーター)のうち、公式HPにDXで業務改善をした事例が公開されている企業27社を選出。
【3選の選定基準】
戦略提案から実行支援まで一気通貫型でDXの推進を支援する企業の中から、以下の条件で3社を選びました。
ベルテクス・パートナーズ(総合系コンサル)…支援先企業(東証プライム市場上場)がDX認定事業者取得した実績があり、成果を継続的に生み出す(自走化・内製化)組織改革をサポートしている。
RIT(IT系コンサル)…どの領域からデジタル化を進めていくべきか診断し、DX推進度診断サービス資料を無料ダウンロードできる。
FPTソフトウェアジャパン(システム系コンサル)…CMMIレベル5、ISO9001:2015、ISO27001:2013など国際基準に則ったシステム開発ができる